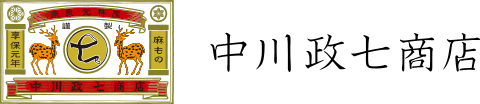現代のライフスタイルに即した新しい茶道の愉しみ方をご提案する、中川政七商店グループの新ブランド「茶論(さろん)」が月一回お届けする「宗慎茶ノ湯噺」。第五回のテーマは「花」です。
「たてる」と「いれる」
日本の花は「たてはな」と「なげいれ」のふたつに大きく分けることができます。
室町時代に書院座敷を飾るために始まった「たてはな」。漢字で書けば立花は、今現在、お稽古事として一般にひろまった「いけばな」の原型です。
そもそも「たてる」とは人間にとって根源的で特別な行為。信州諏訪大社の建御柱の祭など様々な神事によすがが偲ばれるように、いにしえ、花に限らずなにかをたてることは、そのままカミを崇め奉る振る舞いでした。たてられた草木花がそのまま神仏だった、と言い換えても良いかもしれません。やがて、たてることの技術を競いたいという、人の業と欲、さらには処世の方便が加わって近世のいけばなが生まれます。
対して「なげいれ」は、人の力がおよばない、自然の草木花のおのずからなる姿を愛でようとする心のはたらきからです。それを見出したのは、侘びを発見したかつての茶の湯者たちでした。もとい、なげいれの花こそが、侘びとは何かをもの語るなによりの姿かもしれません。
神仏にたてまつることから始まったたてはなと、侘び茶の湯の流行がもたらしたなげいれ。異なるふたつの花は、あたかも、神が孕んだ真逆のたましい、和魂(にぎみたま)と荒魂(あらみたま)のごとき。「たてる」と「いれる」。表裏の風姿が備わって、はじめて日本の花はひとつの躰となるのです。
利休の教えとして名高い「花は野にあるように」のフレーズ。言葉遊びや小手先で花をもてあそぶことで終わらず、一花を前に、一度考えていただきたいものです。
山野草の季節
これから本格的な夏を迎えていきますが、夏の暑い盛りは、茶の湯の花、なげいれにとって楽しみな季節でもあります。5、6月以降、本格的な風炉の季節になると、様々な草花が野山に乱れ咲きます。椿一種に枝もの、枯れ木など、取り合わせの限られた炉の時期の花とは打って変わり、季節ごとの時候の山野草を籠や竹の花入に入れ、たくさんの花との出会いを皆で楽しむ。それが茶会のご馳走の一つとなります。
一期一会の象徴として
少し話は変わりますが、昔、井伊直弼という幕末の大名がいまして、「井伊の赤鬼」として恐れられていました。桜田門外の変で討たれた大名、彼こそが「一期一会」という名句の生みの親であることご存じでしょうか。だれかをもてなすために、伐っていれてしまえば、あとは枯れるのを待つだけ。花は「一期一会」とは何か、目に見えるかたちで教えてくれる大切な存在です。
直弼と同時期を生きた茶人、裏千家11代玄々斎千宗室の言葉に「茶室ノ内ニ掛物釜ヲ始メ、諸道具悉ク死物ニシテ 漸ク火相ト花トノミ活物ナリ。是トテ己亭主未熟ナレバ火相モ花モ死物トナルナリ」があります。茶席の中、掛け軸や釜といった道具をはじめ、ほとんどのモノに命はない。ただ花と、炭のおこりだけが生きている。でも、花も炭火も、取り扱う亭主の技量が未熟だと、すぐに死んでしまう、という教えです。*
道具の取り合わせで一番大切な要素ともいえる季節感ですが、一期一会の象徴として、茶会に過ぎ去っていく時の移ろいや情景をもたらしてくれる花は、上手・下手ではなくて、二度と訪れることのない今日という日を大切にしたいという、亭主もてなしの心映えを表す、もっとも重要な存在として見ていただければと思います。花の造作や珍花奇花を喜ぶのは、人の情として仕方のないことかもしれません。それでも、清々しく活けられた花の何を見るのかということを、おりふし立ち止まって、考えてほしいものです。
*出典:『茶湯一会集』
四清同(しせいどう)
茶の湯の花、その見方を端的に表している教えの一つが、四清同(しせいどう)です。「青竹の清きを切り、水の清きを盛り、花の清きをいれ、心の清きを楽しむ。」
これは、利休の「花は野にあるように」を受けて、江戸時代の茶人・川上不白が更にその心情を仔細に述べたもの。
花や花入などの目に見える美しさではなく、打たれた露をこそ見るべき。茶会が終わる頃には、はじめ席入りした時には、しとど濡れそぼるように打たれていた露が乾いてなくなってしまう。そうかと思えば、かたく閉じていたはずの蕾がほころんで、うっすら色をみせて開き始めている。あるいは、凛と咲いていた山野草が役目を終えて、早や少し萎れかける。そうした変化も侘びの風姿。多くのことを教えてくれます。四清同の本来の意味に沿う努力を忘れずに続けたいものです。
若かりし頃の井伊直弼の”あだ名”
ちなみに、前出の井伊直弼は、若い時からお茶や歌、能に造詣が深く、非常に風流な人物だったそうです。若い頃のあだ名は「ちゃかぽん」でした。これは、お茶の「ちゃ」と、歌の「か」と、能にかかすことのできない鼓の音を想起させる「ぽん」から来ています。多くの兄がいたため、また母親の身分も低く、いずれ殿様になる人物とは誰も思ってすらいなかった当時、井伊藩のお侍さんたちからは、「またちゃかぽんが遊んでいる」と笑われていました。ただ、それはどちらかというと、親しみのこもった愛称に近いものだったと思われます。それに対して、ちゃかぽんと愛された人の晩年のあだ名が、憎しみと恐れの込められた「井伊の赤鬼」と変ずるのですから、人の一生こそは、花ならぬ花。考えさせられます。
2019-07-11
【宗慎茶ノ湯噺】其の五 文月 花

木村宗慎(きむら・そうしん)
1976年愛媛県生まれ。茶道家。神戸大学卒業。少年期より茶道を学び、1997年に芳心会を設立。京都・東京で同会稽古場を主宰。その一方で、茶の湯を軸に執筆活動や各種媒体、展覧会などの監修も手がける。また国内外のクリエイターとのコラボレートも多く、様々な角度から茶道の理解と普及に努めている。 2014年から「青花の会」世話人を務め、工芸美術誌『工芸青花』(新潮社刊)の編集にも携わる。現在、同誌編集委員。著書『一日一菓』(新潮社刊)でグルマン世界料理本大賞 Pastry 部門グランプリを受賞のほか、日本博物館協会や中国・国立茶葉博物館などからも顕彰を受ける。他の著書に『利休入門』(新潮社)『茶の湯デザイン』『千利休の功罪。』(ともにCCCメディアハウス)など。日本ペンクラブ会員。日本食文化会議運営委員長。